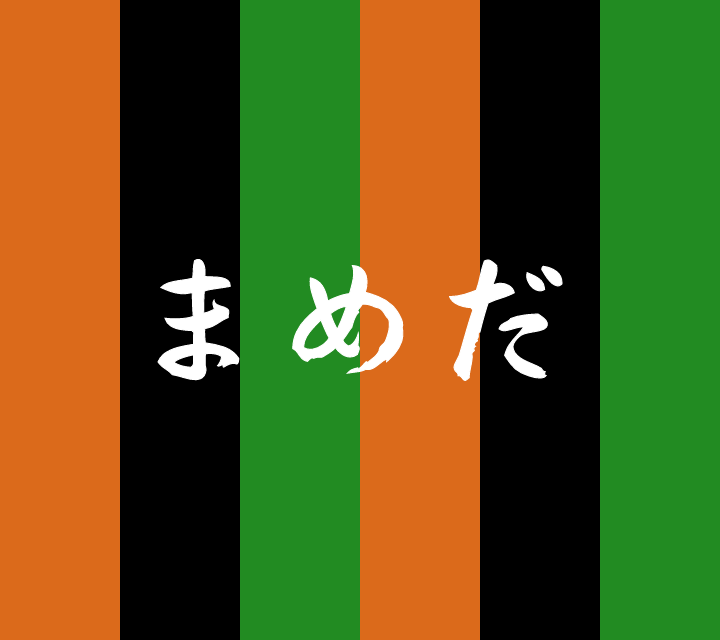まめだ
3行でわかるあらすじ
下回りの役者・市川右三郎が雨の日にまめだ(豆狸)の悪房を受け、トンボを切って退治する。
傷ついた子狸が銀杏の葉を銀銭に変えて実家の膏薬を購入し、治療を試みるが使い方を間違えて死んでしまう。
線香を手向けると秋風で銀杏の落葉が集まり、「狸の仲間から香典が届いた」という温かいオチで終わる。
10行でわかるあらすじとオチ
市川右團次の弟子で下回りの役者・市川右三郎が、トンボの稽古をしていい役をもらおうと努力している。
実家は三津寺前で「本家びっくり膏」という貝殻に詰めた膏薬を商っており、母親が一人で店をやっている。
ある雨の日、道頓堀からの帰り道で僘がズシンと重くなり、まめだ(豆狸)の悪房だと気づく。
右三郎が僘をさしたまま真上にトンボを切ると、ギャーという声とともに黒い物が地面に叩きつけられて逃げていく。
翌日から銀銭箱の勘定が一銭足らず、銀杏の葉が一枚入っている日が続き、紣の着物の子どもが膏薬を買いに来る。
数日後、三津寺の境内で子狸が体中にびっくり膏の貝殻をつけて死んでいるのを発見する。
右三郎は自分が傷つけた狸が銀杏の葉を銀銭に変えて膏薬を購入し、治療しようとしたことを理解する。
和尚に頼んで埋葬し、線香を手向けてお経を上げてもらう。
すると秋風がサーッと吹いて、銀杏の落葉が子狸の死骸の回りに集まり、「狸の仲間から香典が届いた」でオチとなる。
解説
「まめだ」は上方落語の人情噺の代表作で、特に関西で愛されている演目です。
タイトルの「まめだ」は豆狸(小さな狸)のことで、関西地方の方言です。
物語の舞台は大阪の道頓堀、三津寺界周で、江戸時代の歌舞伎の世界と市井の生活がリアルに描かれています。
この落語の最大の特徴は、最初は狸を退治するコミカルな話から始まりながら、最後には深い哀惀と温かい感動を呼ぶ結末へと変化することです。
銀杏の葉が「香典」になるというオチは、日本人の自然観や露皁感を見事に表現した美しい結末であり、単なんるコメディを超えた文学的価値の高い作品として評価されています。
また、「びっくり膏」は実際に大阪にあった有名な膏薬で、当時の聴衆にとって身近な商品であったことが、物語にリアリティを与えています。
あらすじ
市川右團次の弟子で下回りの役者の市川右三郎。
芝居の立ち回りなどで、トンボが器用に切れるようになると、少しはいい役がつくので、一生懸命トンボの稽古をしている。
実家は三津寺前の「本家びっくり膏」という、貝殻に詰めた膏薬を商っている薬屋で今は母親が一人で店をやっている。
右三郎は怪我や打撲などをすればその膏薬を塗ったりして、だんだんいい役もつくようになった。
ある日、芝居が済んで道頓堀から帰ろうとすると雨が降って来たので、なじみの芝居茶屋で傘を借り、太左衛門橋を渡って宗右衛門町を横切り、三津寺筋を西へ入った。
昔はそのあたりは寂しいところだった。
すると傘がズシンと重くなった。
傘をすぼめて見てもなにもない、開くと重くなる。
「まめだ(豆狸)が悪さしやがってんねんな。ようし・・・」と、次に傘が重くなった時に、傘をさしたまま真上にトンボを切った。
するとギャーと何かが地面に叩きつけられて、犬のような黒い物がよろよろしながら逃げて行った。
翌日、芝居を終わって帰って来ると、開いた銭箱を前に、
母親 「勘定が合わんのじゃ」
右三郎 「貝一つで一銭、こんな数えやすいもんあらへんがな。お母さん、ボケたんとちゃうか」
母親 「それが一銭足らんで、銀杏の葉が一枚入ってんねん」
右三郎 「銀杏並木の落葉でも入ったんやろ」
母親 「それに今日はなあ、絣の着物を着た、見かけん陰気な子どもが買いに来たのじゃ。あれが気になるんや」
右三郎 「そんなこと、どうでもええがな。腹ペコでかなわんよって、早よ飯にしてな」、銭箱が一銭足りず、銀杏の葉が一枚入っている日が四、五日続いて、
母親 「今日は勘定はぴったし合って、銀杏の葉も入ってなかったがな。けどあの子どもも買いに来やへんやった」
右三郎 「そうかよかった。きっとうちのびっくり膏が効いて子どもも治ったんやろ」と、一件落着。
当時は芝居は暗いうちに一番太鼓を打って、朝早くから芝居をやっていた。
翌朝早く、右三郎が起きると表の通りがざわついている。
近所の人が、「三津寺(みってら)はんの境内でまめだが死んでるで」、右三郎はハッっと気づくことがあり、飛んで行ってみると、子狸が体中にびっくり膏の貝殻をつけて死んでいた。
右三郎 「お母さん、ちょっと出て来なはれ。・・・このたぬき、わしが殺したようなもんや。
この前、悪さしよってからに懲らしめるためにトンボ切った時、怪我しよったらしい。
銀杏の葉、銭に変えて、うちの膏薬仰山買うて、・・・貝殻から薬出さずにそのまま身体につけて・・・貝殻のままつけたかて何が効くかい。ちょっと言うたら教えたるに・・・可哀想に・・・」
和尚さんに頼んで境内の隅に埋めてもらうこととし、子狸の死骸に線香を手向け、お経を上げてもらう。
近所の人がみな帰ったあと、右三郎親子と和尚が話をしていると、秋風がサーッとと吹いて来て、銀杏の落葉が子狸の死骸の回りにザァーと集まって来た。
右三郎 「お母さん、見てみ、狸の仲間から仰山香典が届いたがな」
落語用語解説
この噺をより深く理解するための用語解説です。
- まめだ(豆狸) – 小さな狸のこと。関西地方の方言で、「豆」は小さいという意味。若い狸や子狸を指します。
- 下回り(したまわり) – 歌舞伎で、端役や立ち回り専門の役者のこと。主役ではなく、群衆や敵役などを演じます。
- トンボ – 歌舞伎の立ち回りで使われる宙返りの技。前方または後方に回転する曲芸的な動作で、派手な演出に使われます。
- 三津寺(みってら) – 大阪市中央区にある真言宗の寺院。正式名称は「七宝山無量壽院三津寺」。地元では「みってらさん」と親しまれています。
- 道頓堀(どうとんぼり) – 大阪市中央区の繁華街。江戸時代から歌舞伎や人形浄瑠璃の芝居小屋が立ち並ぶ芸能の中心地でした。
- びっくり膏(びっくりこう) – 大阪で実際に販売されていた有名な膏薬。打撲や捻挫に効くとされ、貝殻に詰めて売られていました。
- 銀杏(いちょう) – 街路樹として広く植えられている木。秋には黄色く色づいた葉が落ちます。この噺では銀杏の葉が狸の化かしによって銀銭に変わります。
- 絣(かすり) – 織物の一種。糸を染め分けて織ることで模様を出す技法。庶民の普段着として広く着られていました。
- 一銭(いっせん) – 江戸時代の貨幣単位。現代の価値で約100-200円程度。庶民の日常的な買い物に使われました。
- 香典(こうでん) – 葬儀の際に故人に供える金品。この噺では銀杏の落葉が香典に見立てられています。
よくある質問(FAQ)
Q: まめだ(豆狸)は実際に大阪にいたのですか?
A: 狸が大阪市内にいたかは定かではありませんが、江戸時代の大阪周辺には狸が生息していました。「狸の化かし」は全国的に信じられていた民間伝承で、特に傘に化けたり、傘を重くしたりする話は各地に残っています。
Q: なぜ子狸は膏薬の使い方を間違えたのですか?
A: 子狸は人間の真似をして膏薬を買いましたが、貝殻から中身を取り出して塗るという使い方を知らず、貝殻ごと体に貼り付けてしまいました。この無知と悲しさが、聞き手の同情を誘う仕掛けになっています。
Q: 銀杏の葉が銀銭に変わるのは狸の化かしですか?
A: はい、狸が葉っぱを金銭に化かすという民間伝承に基づいています。ただし、この化かしは一時的なもので、時間が経つと元の葉っぱに戻ってしまうとされていました。
Q: オチの「香典が届いた」の意味は?
A: 秋風で銀杏の落葉が子狸の周りに集まったのを、狸の仲間たちからの香典(葬儀への供え物)だと解釈したオチです。自然現象に心情を重ね合わせた、日本人的な美意識が表現されています。
Q: この噺は江戸落語ですか、上方落語ですか?
A: 上方落語の代表的な人情噺です。大阪の地名(道頓堀、三津寺など)や関西弁が使われており、上方落語の特徴が色濃く出ています。
Q: 現代でも演じられていますか?
A: はい、上方落語の人気演目として今でもよく演じられています。特に秋の季節に演じられることが多く、銀杏の落葉が美しい季節感を演出します。
名演者による口演
この噺を得意とした・している落語家をご紹介します。
- 桂米朝(三代目) – 上方落語の人間国宝。この噺を十八番の一つとし、子狸の健気さと哀れさを繊細に表現しました。特に最後の銀杏の落葉の場面は、聞く者の涙を誘う名演として知られています。
- 桂枝雀(二代目) – エネルギッシュな語り口で知られる名人。この噺でも右三郎のトンボの場面を視覚的に表現し、コミカルさと哀愁を見事に演じ分けました。
- 桂ざこば(二代目) – 豪快な語り口が特徴。母親と右三郎のやり取りを温かく描き、最後の香典の場面では静かな感動を呼びます。
- 桂南光(三代目) – 「べかこ」の愛称で親しまれる人気落語家。軽妙な語り口で、笑いと涙のバランスを巧みに取った高座を見せます。
- 桂文枝(六代目) – 現代的な解釈を加えながらも、古典の良さを残した演出。子狸の健気さを強調し、若い世代にも共感を呼ぶ工夫をしています。
関連する落語演目
狸が登場する古典落語



動物の化かしを題材にした落語



人情噺の名作



大阪を舞台にした上方落語


この噺の魅力と現代への示唆
「まめだ」の最大の魅力は、最初はコミカルな狸退治の話から始まりながら、最後には深い哀愁と温かい感動を呼ぶ結末へと変化する構成にあります。右三郎がトンボを切って狸を退治する場面は痛快ですが、その後の展開で聞き手の感情は大きく揺さぶられます。
特に印象的なのは、子狸が銀杏の葉を銀銭に変えて膏薬を買いに来る場面です。傷ついた体を治そうと必死に人間の真似をする子狸の健気さは、聞く者の心を打ちます。しかし、膏薬の使い方を知らず、貝殻ごと体に貼り付けてしまう無知さが、さらに哀れさを増しています。
「貝殻から薬出さずにそのまま身体につけて・・・ちょっと言うたら教えたるに」という右三郎の言葉には、深い後悔と哀惜の念が込められています。人間と動物の間にある決定的な知識の差、そしてコミュニケーションの不可能性が、この悲劇を生んだのです。
最後の銀杏の落葉が香典になるというオチは、日本人の自然観や死生観を見事に表現した美しい結末です。秋風で舞い落ちる銀杏の葉を、狸の仲間からの香典と見立てる発想は、自然現象に心情を重ね合わせる日本人的な美意識の表れです。
現代の視点から見ると、この噺は「善意の行為が意図せぬ悲劇を生む」というテーマを含んでいます。右三郎は悪戯をする狸を懲らしめただけで、殺すつもりはありませんでした。しかし、その行為が子狸の死につながってしまう。人間の行動が予期せぬ結果を生むという教訓は、環境問題や野生動物との共生を考える現代社会にも通じるものがあります。
また、この噺は親子の絆も描いています。右三郎と母親の温かい関係、そして子狸が必死に傷を治そうとする姿は、親を思う子の心を表しているとも解釈できます。
実際の高座では、右三郎のトンボの場面、子狸が膏薬を買いに来る場面の描写、そして最後の銀杏の落葉の表現など、演者の技量が問われる場面が多くあります。特に最後の場面は、静かな感動を呼ぶために、演者の繊細な表現力が必要です。
機会があれば、ぜひ秋の季節に生の落語会でお楽しみください。銀杏の落葉が美しい季節に聴くと、より一層この噺の情緒が心に染みます。笑いと涙、そして日本の美意識を存分に味わえる上方落語の名作です。