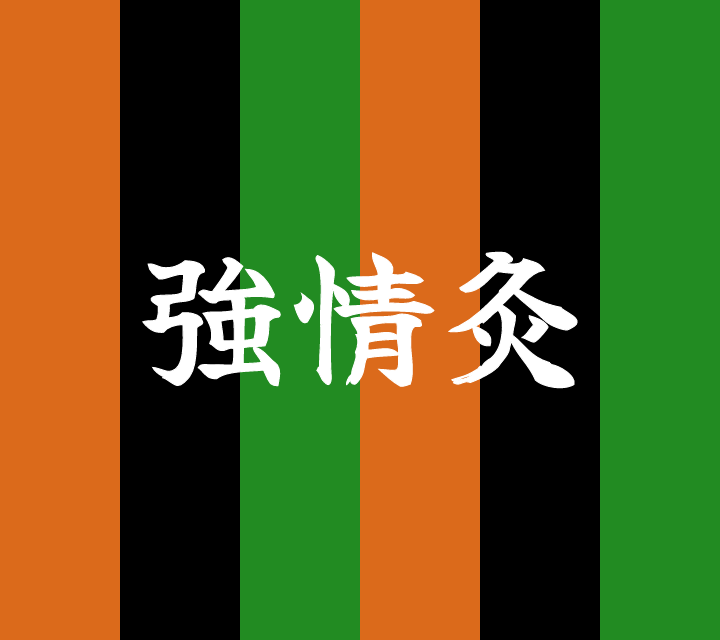強情灸
3行でわかるあらすじ
源さんが灸を据えてもらった熱い話を聞いた熊さんが、「灸なんか熱くない」と強情を張る。
熊さんはもぐさを山盛りにして火をつけ、石川五右衛門や八百屋お七の話を出して強がる。
しかし熱さに耐えきれずもぐさを払い落とし、「五右衛門はさぞ熱かったろう」と本音を漏らす。
10行でわかるあらすじとオチ
長屋の源さんが腰痛で薬湯に入ったがのぼせて倒れ、逆に冷やされてしまった。
湯にいた伊勢六の隠居が腰痛には灸が効くと言うので据えてもらうと、とんでもなく熱い。
隠居は「上へ上へと据えるんだ」と教え、源さんは隣のかみさんに据えてもらう。
上へ上へと据えていったら頭の上に来てしまい、ここからは下って目の玉だがどうしようかと悩んでいる。
そこへ気短で強情な熊さんがやって来て、「灸なんか熱いもんか」と癌にさわった。
熊さんは片腕をまくりもぐさを山のように乗せ、「ソフトクリームのようだ」と源さんが呆気に外観。
熊さんは石川五右衛門や八百屋お七、かちかち山の狸の話を引き合いに出して強がる。
しかし線香で火をつけて団扇で扇ぐと、猫烈な熱さに目を白黒し顔を真っ赤にして苦悶する。
とうとう我慢できずにもぐさを払い落とし、源さんに「石川五右衛門がどうした」と聞かれて「五右衛門はさぞ熱かったろう」と本音を漏らす。
解説
「強情灸」は元々上方落語の「やいと丁稚」という演目が東京に移植されたもので、5代目古今亭志ん生が特に得意とした古典落語の名作である。オチは「ぶっつけオチ」と呼ばれる形式で、登場人物の本音が漏れて話が終わる構成となっている。
この演目の魅力は、「武士は食わねど高綾」の江戸っ子気質をこれでもかというほど誇張した点にある。強情な熊さんは灸の熱さを侮っておきながら、最終的にはその熱さに屈服してしまう。石川五右衛門や八百屋お七、かちかち山の狸などの武勇伝や昔話を引き合いに出して強がるものの、結局は素直に熱さを認めるという、人間らしい結末が笑いを誘う。
この演目は「見る」要素が強く、熊さんがだんだん表情が変わり、顔が真っ赤になっていくところが見せ場となっている。上方版の「やいと丁稚」ではお灸を使った折櫃という設定だったが、東京版では友人同士の意地の張り合いという、より軽妙で親しみやすい設定に変更されている。江戸時代から明治・大正時代にかけての下町気質を色濃く反映した、古典落語の名作の一つである。
あらすじ
十人十色、人それぞれ顔形が違うように気性も違う。
気の短い人、長い人、無精な人、強情な人など様々だ。
長屋の源さんは陽気の代り目で腰が痛く、温めた方がいいというので近くのフロ屋の薬湯に入ったが、長く入り過ぎてのぼせて倒れて、水をかけられ逆に冷やされてしまった。
湯にいた伊勢六の隠居が腰痛には灸が効くと言うので据えてもらったがその熱いこと。
後は自分で据えろ、上へ上へと据えるんだと言われ、一人では据えられないので、隣のカミさんに据えてもらったが、上へ上へ据えて行ったら、頭の上に来てしまいここからは下って目の玉だがどうしようかなんて悩んでいる。
隣のカミさんもこんな据え方は初めてだと言ってはいたのだが。
そこへやって来たのが友達の熊さんで、気短で強情な男だ。
源さんから灸を据えてもらった話しを聞くうちに、あまり熱い、熱いと言うものだから癪にさわり、「灸なんか熱いもんか」といって、片腕をまくりもぐさを山のように乗せた。
源さんはまるでソフトクリームのようだなんて呑気に見ていたが、熊さんは線香で火をつけようとする。
源さんはやめた方が言いと止めるが、熊さんは石川五右衛門は釜ゆでにされながら、「石川や 浜の真砂は尽くるとも むべ山風を嵐といふらむ」と、 辞世の歌を詠んだとか、八百屋お七は娘ながらに火あぶりの刑になった、かちかち山の狸は背負った柴に火をつけられた。
それに比べればこんな灸はぬるま湯につかったようなもの、蚊に刺されたようなもんだと、悪強情丸出しだ。
そして線香でもぐさのてっぺんに火をつけた。
ゆらゆらと上がる煙を見て、「♪小諸出で見りゃあ浅間の煙~だ」、全然熱くないなんて言っているが、まだ火が下へ回っていないのだから、そりゃあそうだが。
よせばいいのに団扇(うちわ)で仰ぎ始め、そのうちに火が回ってきて猛烈の熱さになってきた。
目を白黒、顔を真っ赤にして「石川五右衛門は・・・、八百屋お七は・・・石川五右衛門は・・・・」、ついに腕がもぎとられそうな熱さに我慢できずに、もぐさを払い落した。「あぁ、冷てぇ」、なんてまだ悪強情だが、
源さん 「石川五右衛門がどうした」
熊さん 「五右衛門はさぞ熱かったろう」
落語用語解説
この噺をより深く理解するための用語解説です。
- 灸(きゅう) – もぐさを皮膚に置いて火をつけ、熱刺激で治療する東洋医学の療法。江戸時代から庶民に広く親しまれた民間療法でした。
- もぐさ – ヨモギの葉の裏にある綿毛を精製したもので、灸に使用します。火をつけると徐々に燃えて皮膚に熱を伝えます。
- 薬湯(くすりゆ) – 薬草などを入れた風呂。江戸時代の銭湯では、季節ごとに菖蒲湯や柚子湯などの薬湯が提供されました。
- 石川五右衛門 – 安土桃山時代の盗賊。豊臣秀吉の命により、京都三条河原で釜茹での刑に処されたとされる伝説的人物です。
- 八百屋お七 – 江戸時代前期、放火の罪で火あぶりの刑に処された少女。恋人に会いたい一心で放火したという悲恋物語が有名です。
- かちかち山 – 日本の昔話。悪戯な狸がウサギに背負った柴に火をつけられて火傷をする話で、落語でもよく引用されます。
- ぶっつけオチ – 落語のオチの形式の一つ。突然本音が出たり、意外な一言で幕になる落とし方を指します。
よくある質問(FAQ)
Q: 灸は本当にそんなに熱いのですか?
A: 現代の灸は温度管理された温灸などもありますが、江戸時代の直接灸は確かに熱いものでした。ただし、この噺の熊さんのように山盛りにするのは誇張表現で、実際には米粒大のもぐさを使います。
Q: なぜ源さんは頭の上に灸を据えることになったのですか?
A: これは落語的な誇張表現です。「上へ上へと据える」という指示を文字通り受け取り、腰から背中、首、頭と上がっていった結果、頭頂に達してしまったという笑い話です。
Q: 「やいと丁稚」との違いは何ですか?
A: 上方落語の「やいと丁稚」は、丁稚が主人から灸の折檻を受けるという設定です。東京版の「強情灸」は友人同士の意地の張り合いという、より対等で親しみやすい設定に変更されています。
Q: なぜ石川五右衛門や八百屋お七が引用されるのですか?
A: 熊さんが灸の熱さに耐えるため、火に関する有名な逸話を引き合いに出して自分を鼓舞しているのです。しかし結局その熱さに負けることで、逆に彼らの苦しみを実感するという笑いになっています。
名演者による口演
この噺を得意とした・している落語家をご紹介します。
- 古今亭志ん生(五代目) – この噺を東京で広めた昭和の大名人。熊さんの強情さと、徐々に顔色が変わっていく様子を見事に演じました。
- 古今亭志ん朝(三代目) – 父・志ん生の芸を継承し、より洗練された語り口で熊さんの心理変化を表現しました。
- 柳家小三治(十代目) – 人間国宝。丁寧な人物描写で、江戸っ子の照れと強情さを絶妙に演じ分けます。
関連する落語演目
長屋の人間関係を描いた古典落語
この噺の魅力と現代への示唆
「強情灸」は、意地とプライドが招く自業自得を描いた作品として、現代にも通じる普遍的なテーマを持っています。
最大の魅力は、熊さんの心理変化を視覚的に表現できる点です。最初は余裕で強がっていた熊さんが、徐々に顔色を変え、最後には本音を漏らす。この変化を演者がどう表現するかが見せ場となります。落語は基本的に座ったまま演じる芸能ですが、この噺では顔の表情や身体の震えなど、非言語的な表現が重要な役割を果たします。
江戸っ子の「武士は食わねど高楊枝」という気質は、現代でも「見栄を張る」「弱みを見せたくない」という形で残っています。SNS時代の現代では、むしろこの傾向は強まっているかもしれません。他人の前で弱音を吐けない、失敗を認められない。そんな現代人の姿が、熊さんの強情さに重なります。
興味深いのは、熊さんが引用する石川五右衛門や八百屋お七、かちかち山の狸という比喩です。これらは江戸時代の共通知識として、聴衆にすぐ伝わる例えでした。現代でも、誰もが知っている共通の文化的基盤があることで、コミュニケーションがスムーズになります。
また、この噺は「経験に勝る学びなし」という教訓も含んでいます。熊さんは他人の話を聞いて「熱くない」と判断しますが、実際に体験してみて初めて真実を知ります。現代でも、他人の忠告を聞かず自分で失敗してから学ぶ人は少なくありません。
最後のオチ「五右衛門はさぞ熱かったろう」は、自分の体験を通じて他者への共感が生まれる瞬間を描いています。痛みや苦しみは、実際に体験して初めて真に理解できる。この普遍的な真理を、笑いに包んで提示しているのがこの噺の深さです。
実際の高座では、熊さんの顔色が変わっていく様子や、もぐさを払い落とす仕草など、演者の身体表現が見どころです。ぜひ実際の高座や動画でお楽しみください。