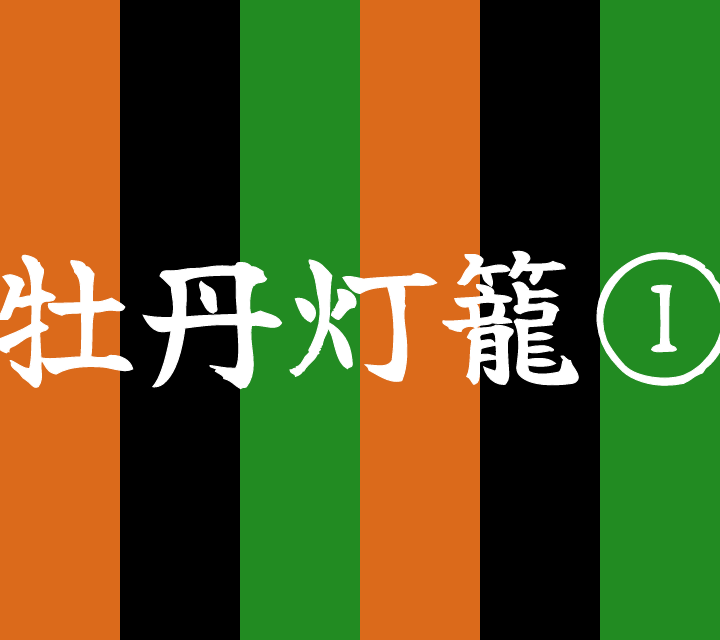牡丹灯籠①
3行でわかるあらすじ
根津の美男・萩原新三郎が知り合いの医者・山本志丈に誘われて柳島の別荘で美女お露と出会い一目惚れするが、お露は既に死んでいた幽霊だった。
毎晩牡丹の灯籠を提げたお米を先に、お露が通ってきて新三郎と契りを結ぶが、伴蔵と易者の白翁堂勇斎に幽霊だと教えられ死相が出ていると警告される。
新三郎はお札を貼り海音如来を身につけて経を読んで身を守るが、最後にお露が迎えに来る怪談噺の代表作。
10行でわかるあらすじとオチ
根津の美男・萩原新三郎が医者の山本志丈に誘われて柳島の別荘を訪れる。
そこで美女お露と一目惚れし、お露も「また来なければ死んでしまう」と言う。
数ヶ月後、志丈からお露と女中お米が恋い焦がれて死んだと聞かされる。
新三郎が念仏三昧で暮らしていると、盆の夜に牡丹灯籠を提げたお露とお米が現れる。
毎晩通ってきて新三郎と契りを結ぶが、伴蔵が覗くと腰から下のない幽霊だった。
易者の白翁堂勇斎が新三郎を診ると「二十日以内に死ぬ相」が出ている。
新幡随院で牡丹の灯籠が置かれた飯島平左衛門の娘と女中の墓を発見する。
幽霊除けのお札と海音如来を身に付け、家に籠って経を読んで身を守る。
寛永寺の八つの鐘が響く頃、いつものカランコロンという下駄の音が聞こえる。
第二話へ続く「引き」で終わり、新三郎とお露の運命は次回へ持ち越される。
解説
「牡丹灯籠」は、古典落語の中でも最も有名な怪談噺の一つで、三遊亭圓朝の代表作として知られています。この第一話は、美男の萩原新三郎と美女の幽霊お露との運命的な出会いから、幽霊との恋愛関係、そして新三郎が幽霊だと気づいて身を守ろうとするまでを描いています。
物語の構成は非常に巧妙で、最初は普通の恋愛話として始まり、徐々に怪談の要素が明かされていく展開が見事です。お露が「また来てくださらなければ私は死んでしまいますよ」と言った言葉が、後に彼女が既に死んでいたという伏線になっている点など、細部まで計算された構成となっています。
牡丹の灯籠という小道具は、美しさと不気味さを同時に表現する絶妙な選択で、カランコロンという下駄の音とともに、聴衆に強烈な印象を残します。新三郎の心境の変化、伴蔵の恐怖、易者の警告など、登場人物それぞれの心理描写も丁寧に描かれており、単なる怪談を超えた人間ドラマとしても優れた作品です。
第一話の最後は、新三郎がお札と海音如来で身を守り経を読んでいるところで中断され、続きは第二話へと続きます。この「引き」の技法も、聞き手の興味を次回へとつなげる巧妙な演出となっています。
あらすじ
根津の清水谷に田畑や長屋を持ち、その上りで生計を立てている浪人の萩原新三郎。
今年二十一で生まれつきの美男だが、内気で家に閉じこもって本ばかり読んでいる。
ある日、知り合いのお幇間医者の山本志丈が誘い来て亀戸の臥龍梅を見に行く。
その帰路に、
志丈 「・・・僕の知り合いの飯島平左衛門の柳島の別荘に参りましょう。たいそう別嬪な嬢様と女中の二人暮らしですから冗談でも申して来ましょう」と、訪れた別荘で新三郎が出会ったのが今年十七のめっぽうな美人のお露さん。
初心な二人は顔を合わせた途端にお互いにのぼせ上がってしまった。
帰り際にお露さん、「また来てくださらなければ私は死んでしまいますよ」、この言葉が新三郎の耳に残り、しばしも忘れることはなかった。
新三郎はお露に会いたくてしょうがないが、内気で一人で逢いに行く勇気がない。
また山本志丈が来て誘ってくれるだろうと期待しているが、二月、三月、四月を過ぎても志丈は来ない。
お露のことを思い詰めて悶々とした日々を暮らして食事ものどを通らず、悪夢にうなされたりしている六月のある日、やっと志丈が訪ねて来た。
新三郎 「・・・柳島へ菓子折りの一つも持ってお礼に行きたいと思っているのに、・・・」
志丈 「お嬢様はお亡くなりになりました。
実はこの間、柳島へあなたをお連れした時に、お二人がすぐにぞっこんのご様子。
飯島様にこの志丈が手引きしたと思われては困るゆえ、遠ざかっておりました。・・・お嬢様はあなたに恋い焦がれて死んでしまったそうです。女中のお米さんも看病疲れで後を追うように死んだそうで・・・」、志丈は面倒に巻き込まれるのはご免という体で帰ってしまった。
新三郎はそれからというものお露さんの俗名を書いて仏壇に供えて、念仏三昧で暮らしていたが、盆の十三日の夜、お露さんのことを思いながら冴えわたる月を眺めていると、カランコロンカランコロンと下駄の音が響いた。
見ると牡丹芍薬の灯籠を提げたお米を先に、後から髪は文金の高髷、秋草色染めの振袖姿のお露さんだ。
お米も新三郎に気づいて、
お米 「まあ、萩原様、あなたはお亡くなり遊ばしたと聞いておりましたが・・・」
新三郎 「あなた方こそお亡くなりになったと・・・」、二人を中に入れると、
お米 「あなたがお亡くなりなったと聞いてお嬢様は尼になると申されましたが、親御の飯島様は婿を取れと・・・柳島の別荘にも居られなくなり、今は谷中の三崎あたりの粗末な家に移って、私の手内職などでどうにか暮らしをつけております。今日はお盆で方々お参りしてこんなに遅くなって・・・」
二人とも新三郎のところへ泊まり、次の晩もその次も、雨の日も風の日も続き、お露と新三郎の仲はまるで膠(にかわ)のようになって行った。
新三郎の孫店に住んでいる伴蔵が、毎夜新三郎の家に女が通って来るのに気づき、不審に思って、戸の隙間から中の様子を聞くと、
お露 「・・・たとえこのことがお父様に知れて手打ちになりましても、お見捨てなさると聞きませんよ・・・」、どんな女かと覗くと、骨と皮ばかりの痩せた女が新三郎の首へかじりついている。
よく見ると腰から下はないようで、これぞまさに幽霊だ。
びっくりして伴蔵は家に逃げ帰った。
翌朝、伴蔵は新三郎の相談相手となっている易者の白翁堂勇斎のところへ行く。
始めは伴蔵の話を信じなかった勇斎だが、「・・・幽霊と偕老同穴の契りを結べば必ず死ぬものだ」、勇斎と伴蔵は新三郎の家に急ぐ。
勇斎は天眼鏡で新三郎の顔を見て、「二十日を待たずして必ず死ぬ相が出ている」と宣告する。
新三郎は今までのいきさつを話し、三崎村に住んでいるというお露とお米の家を探しに行くが見つからない。
あきらめて帰ろうと新幡随院の境内を通るとお堂の前に牡丹の花の綺麗な灯籠が置いてある新墓がある。
僧に聞くと、飯島平左衛門の娘と女中の墓という。
やっと幽霊に惚れられているのを納得した新三郎、勇斎の取り計らいで、新幡随院の和尚から幽霊除けのお札をもらい、死霊除けの金無垢の海音如来像借りて帰り、家の回りにお札をべたべたと貼りつけ、海音如来を肌身につけ、家に籠って雨宝陀羅尼経を大声で読み始めた。
寛永寺の八つの鐘が響くころ、いつものようにカランコロンカランコロンと駒下駄の音高く、・・・さて、新三郎と幽霊のお露さんの運命や如何に。
落語用語解説
この噺をより深く理解するための用語解説です。
- 幇間(ほうかん) – 太鼓持ちとも呼ばれ、宴席で座を盛り上げる職業的な遊び人。山本志丈は「お幇間医者」と呼ばれ、医者でありながら太鼓持ちのような軽薄な性格の人物として描かれています。
- 文金の高髷(ぶんきんのたかまげ) – 江戸時代後期の武家の女性や裕福な町人の娘が結った髪型。島田髷の一種で、華やかで格調高い髪型として知られています。
- 海音如来(かいおんにょらい) – 死霊除けの霊験あらたかな仏像。物語では金無垢で作られた小さな仏像として登場し、新三郎を幽霊から守る重要なアイテムとなります。
- 雨宝陀羅尼経(うほうだらにきょう) – 災いを除き、福を招くとされる経文。幽霊除けのために新三郎が読誦する経典です。
- 孫店(まごだな) – 大家から借りた店子がさらに又貸ししている部屋。経済的に困窮している人が住むことが多く、伴蔵の生活状況を表しています。
- 天眼鏡(てんがんきょう) – 易者が使う拡大鏡や占い道具。白翁堂勇斎が新三郎の死相を見るのに使用します。
- 偕老同穴(かいろうどうけつ) – 生きている間は共に老い、死んでも同じ墓に入るという夫婦の深い契りを表す言葉。
よくある質問(FAQ)
Q: 牡丹灯籠は実話に基づいているのですか?
A: 原作は中国明代の小説『剪灯新話』の「牡丹灯記」ですが、三遊亭圓朝が江戸の風土に合わせて翻案しました。根津、柳島、谷中など実在の地名を使い、江戸時代の風俗を織り込んだ創作怪談となっています。
Q: なぜ牡丹の灯籠なのですか?他の花ではダメだったのでしょうか?
A: 牡丹は中国では「百花の王」と呼ばれ、美しさと妖艶さの象徴です。また、牡丹は死者への手向けの花としても使われ、美しさと不気味さを併せ持つ花として、幽霊が持つ灯籠にふさわしいとされました。
Q: カランコロンという下駄の音は実際に聞こえるのですか?
A: 落語の演出では、演者が扇子や手拍子で下駄の音を表現します。この音は聴衆に強烈な印象を与え、幽霊の接近を知らせる効果的な演出となっています。実際の高座では、演者によって音の表現が異なり、それぞれの個性が表れます。
Q: 牡丹灯籠は全部で何話構成なのですか?
A: 通常は3部構成で演じられます。第1話が新三郎とお露の出会いから幽霊だと判明するまで、第2話が伴蔵夫婦の裏切りと金銭欲、第3話が因果応報の結末を描きます。ただし、演者によって構成や話数が異なることもあります。
Q: 現代でも「牡丹灯籠」は人気があるのですか?
A: はい、現在でも落語の怪談噺の代表作として頻繁に上演されています。特に夏の納涼寄席では定番演目となっており、映画化やドラマ化も繰り返しされている人気作品です。
名演者による口演
この噺を得意とした・している落語家をご紹介します。
- 三遊亭圓朝(初代) – この噺の作者。速記本『怪談牡丹灯籠』として明治17年に刊行。怪談話術の名手として知られ、近代落語の祖と呼ばれる。
- 三遊亭圓生(六代目) – 昭和の名人。重厚な語り口で、新三郎の心理描写と幽霊の不気味さを見事に表現。長編物の第一人者として知られる。
- 林家正蔵(八代目・彦六) – 江戸前の粋な語り口で、怪談の怖さと人情の機微を巧みに描いた。特にカランコロンの下駄音の表現が印象的。
- 柳家喬太郎 – 現代の名手。古典の格調を守りながら、現代的な解釈も加えて若い世代にも人気。怪談噺の名手として評価が高い。
関連する落語演目
続編・関連作品
同じく「怪談噺」の古典落語
恋愛要素を含む古典落語
この噺の魅力と現代への示唆
「牡丹灯籠」第一話は、単なる怪談話を超えた、人間の心理を深く掘り下げた作品です。新三郎とお露の純愛から始まり、それが死を超えた執着となり、最終的には恐怖へと変わっていく展開は、恋愛の持つ美しさと恐ろしさの両面を見事に描いています。
現代においても、この物語は様々な解釈が可能です。SNS時代の「つながり過ぎる」人間関係、ストーカー問題、執着と愛情の境界線など、現代的なテーマとしても読み解くことができるでしょう。新三郎が幽霊だと分かっても、なお惹かれてしまう心理は、危険だと分かっていても離れられない関係性の象徴とも言えます。
カランコロンという下駄の音は、演者によって表現が異なり、それぞれの個性が光ります。ある演者は恐怖を強調し、別の演者は悲しさを滲ませ、また別の演者は妖艶さを表現します。この音の表現一つで、物語の印象が大きく変わるのも、落語という話芸の奥深さです。
牡丹の灯籠という美しい小道具も、この物語の魅力の一つです。牡丹は「百花の王」と呼ばれる豪華な花ですが、同時に散り際の儚さも持ち合わせています。生と死、美と醜、愛と恐怖という相反する要素を一つの物語に凝縮した、日本の怪談文学の最高傑作と言えるでしょう。
実際の高座では、約1時間以上かけて演じられることもあり、聴衆を物語の世界に引き込む演者の技量が試される大作です。夏の納涼寄席では必ず演じられる定番演目ですので、ぜひ一度、生の高座でお楽しみください。